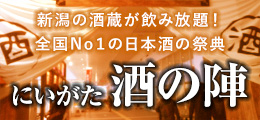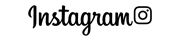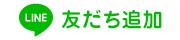雪椿酒造(株)
厳しい冬に耐え、春には美しい花が咲く「ユキツバキ」の姿を酒造りの理想としたいという思いが込められています。
1000石~1500石という規模で昔ながらの手造りの技を守り、高品質の純米酒に限定した酒造りを行っているユニークな酒蔵です。

周囲の自然と環境
雪椿酒造がある加茂市は三方を山に囲まれています。
酒蔵は加茂の中心通りに位置し、東に粟ヶ岳、西には弥彦山を眺望できる風光明媚な場所です。
その南東部にある粟ヶ岳は標高1,293mの山で、日本三百名山の一つとして数えられています。

その山を水源に、町のシンボルとなっている加茂川が形成されています。
この川は町の中心部を流れており、町のシンボルとなっています。
水中にはギンブナやウグイのほか、メダカやアカザといった日本古来の魚類が生息している非常にきれいな河川です。
川の周囲は、河川改修により川幅が広げられ、河川敷には公園や花壇が整備されています。
毎年、夏にこの河川敷で夏祭りが行われる他、子供の日が近づくと大量の鯉のぼりが河川に並ぶイベントが有名となっています。
春の加茂川沿いに並ぶ500匹の鯉のぼりは圧巻で、家族連れなどでゆっくり堪能できます。

そんな加茂市の起源は平安時代に遡ります。
青海神社の鳥居前町として栄えたのが町の起源と言われています。
町の中心には青梅神社がありますが、西暦927年もの昔に建立された歴史ある建物です。
平安時代にさかのぼるとこの土地は、京都の賀茂神社の領地となっていました。
京都の上賀茂神社と下賀茂神社の祭神が分霊されたことから、「加茂」と呼ばれるようになりました。
このように古くから京都との関わりがあった事で由緒ある神社や寺院の多い事や、中心街の落ち着いた町並みから「越後の小京都」とも呼ばれる情緒ある町なのです。
新潟県のシンボルの樹木「雪椿」
この蔵の創業は1806年に丸若酒造として酒造りを始めました。
「雪椿」は、1967年「ユキツバキ」が県の木に指定されたことを記念して名付けられました。
加茂市は、新潟県を代表する樹木である「ユキツバキ」の群生地として有名であったことに由来します。
日本海側の多雪地帯に分布し雪解けを待って咲くユキツバキは厳しい冬に耐え、雪解けとともに深紅の花を咲かせます。
この鮮烈なイメージを酒にも持たせたいという想いから、酒名を「雪椿」と名付けたそうです。
その後、1987年に「世界鷹小山家グループ」に加入します。
これにより蔵は、資金的に安定した酒造りができる体制となりました。

小山グループとは、埼玉県の小山酒造を中心とした酒蔵のグループです。
創業者の小山屋又兵衛は、1780年頃に灘・伊丹・伏見にて酒造りの技術を習得し、現在のさいたま市にて酒造業を開始しました。
1970年代からは、大量生産・営業の全国展開を開始しました。
その後、全国の清酒メーカーを合併・買収する形で発展し、世界鷹小山家グループとしてれ地域毎の技術を活かした分社経営を行っています。
2018年は全国第4位の酒造量を誇る最大手の清酒メーカーのひとつでもあります。
雪椿酒造はこのような大手の資本によって、高度な酒造りの技術をいちはやく導入することができたのです。
そんな雪椿酒造の大きな特徴と言えば純米酒だけを専門に造るところではないでしょうか。
この蔵は2011年に純米酒だけをつくるいわゆる「純米蔵」になりました。
その理由は、もともと純米吟醸酒や純米酒などの比率が8割以上と高かったことが挙げれます。
さらに純米酒造りに特化し、個性を出すことに専念をしたのでしょう。
手仕事の重要性を熟知
アルコール添加を行わない純米酒は、米の旨みがしっかりと感じられ、蔵の個性が出やすいと言われています。
ですから軽すぎず、重すぎず、調和がとれた味作りが必須となります。
そこで雪椿酒造がこだわったのは、何杯でも飲むことができる透明感のある「淡麗旨口」の純米酒を目指しました。
それには、手仕事を中心とした酒造りが必要だと彼らは言います。
資金的な余裕があった雪椿酒造は、全て機械化することも可能であったでしょう。
しかし、蔵に入ると、大勢の人たちが所狭しと作業をしている様子がわかります。
彼らは機械に頼りきらず、できる限り人の手で製造を行おうとしています。
特に原料処理は10㎏ずつ米を洗い限定吸水を行うほど手仕事を重視しています。
この酒米に水を吸わせる作業は、酒造りにおいて非常に重要です。
その後の工程である蒸米や麹作りに大きく影響するからです。
しかしこの給水作業は、酒米の種類や精米歩合によって大きく時間が異なります。
またその年の米の出来方によっても給水時間が変わってきます。
特に暑い日が続くと、高温障害がおこり米が割れやすくなるのです。
このように酒米とは非常にデリケートな原材料なのです。
雪椿酒造では、給水にサナ板付き浸漬タンクという手動の機械を導入しています。
この給水に使う特殊なタンクの中には、たくさん穴が空いたサナ板という板が付いた特殊な構造です。
これにより、一気に水に浸し、時間が着たら短時間で排水をすることができます。
また洗浄もしやすく、機械が常に清潔な状態を保てます。
機械と言っても人力で使用し、人の目は欠かせません。
さらに業界では、非常に画期的な発明と言われています。
雪椿酒造はこのような機械を使い、必ず人の手と目によって、米の状態に応じた給水作業を行います。
他にも人の手による重要さを熟知しています。
機械化した蔵では、連続蒸米機を使い、ベルトコンベアの要領で米を蒸します。
しかしこの蔵では蒸米作業は人手による「抜掛け法」で行います。
これは白米を甑の中に並べる方法の一つで、まず少量の白米を甑の中に平らに置き、蒸気が吹き抜けぬけるのを待って、さらに適量の白米を置くことを繰り返す方法です。
これにより機械ではできない、米の旨みが出るのだそうです。

製麹には10㎏盛りの麹箱を使い、これも機械ではなく人が作業を行っています。
必然的に造り手の連携は重要になり、和やかな雰囲気になるとのことです。
だから雪椿酒造はチームワークの取れた暖かい職場になるのです。
それらの努力もあって雪椿酒造は多くの賞を総なめにしています。
杜氏同氏がガチンコで闘うと言われている「越後流酒造技術選手権大会」首位になったこともあります。
「全国新酒鑑評会」で金賞、「関東信越国税局酒類鑑評会」で吟醸部門、純米部門ダブルで優秀賞。さらに2年連続の受賞などし、純米蔵として屈指の存在となりました。
雪椿酵母仕込みの酒
またこの酒蔵では「ユキツバキ」の花から採取した酵母を使用するなど、地域に寄り添った商品も開発しています。
蔵の裏手には加茂山公園があり、そこにはユキツバキが咲き乱れています。
この花の酵母で、社名にふさわしい酒が造れないものかと、2005年から酵母を探し始めました。
しかし花から酵母を採取できる確率は非常に低く、半ばあきらめていました。
3年が経過した時、偶然にも酵母を発見することができたようで「雪椿酵母仕込」の酒が誕生しました。
この雪椿の酵母は、発酵力が強く酸味がしっかりしたキレのいいお酒が誕生しました。

| 全国新酒鑑評会 | ||
| 平成21年5月 | 第97回 | 金賞 |
| 平成23年5月 | 第99回 | 金賞 |
| 平成24年5月 | 第100回 | 金賞 |
| 平成25年5月 | 第101回 | 入賞 |
| 平成26年5月 | 第102回 | 入賞 |
| 平成27年5月 | 第103回 | 金賞 |
| 平成28年5月 | 第104回 | 入賞 |
| 平成29年5月 | 第105回 | 金賞 |
| 平成30年5月 | 第106回 | 金賞 |
| 令和元年5月 | 第107回 | 金賞 |
| 関東信越国税局酒類鑑評会 | ||
| 平成20年11月 | 第79回 | 優秀賞 |
| 平成21年11月 | 第80回 | 優秀賞 |
| 平成24年11月 | 第83回 | 優秀賞 |
| 平成26年11月 | 第85回 | 優秀賞 |
| 平成27年11月 | 第86回 | 優秀賞 |
| 平成28年11月 | 第87回 | 優秀賞 |
| 平成29年11月 | 第88回 | 優秀賞 |
| 平成30年10月 | 第89回 | 優秀賞 |
| 令和元年10月 | 第90回 | 優秀賞 |
他にも多数受賞歴あり
雪椿酒造(株)製造銘柄
雪椿酒造(株)新着情報
- 2022.10.12 雪椿酒造(株)白瀧酒造(株)新潟銘醸(株)高の井酒造(株)吉乃川(株)菊水酒造(株)長谷川酒造(株)(株) DHC酒造(株)越後酒造場越後桜酒造(株)(株)北雪酒造越つかの酒造(株)白龍酒造(株)中川酒造(株)金鵄盃酒造(株)大洋酒造(株)
- 全国燗酒コンテスト2022結果
全国燗酒コンテスト
新潟県内の酒蔵は下記の通りに受賞しました。
お値打ちぬる燗部門
★最高金賞
純米酒 PAIR 吉乃川株式会社
越乃白雁 黒松 中川酒造株式会社
越乃雪椿 純米吟醸「花」 雪椿酒造株式会社
大吟醸 越後桜 越後桜酒造株式会社★金賞
長者盛 百萬長者 新潟銘醸株式会社
たかの井 清酒 高の井酒造株式会社
濃醇魚沼 純米 白瀧酒造株式会社
越乃梅里 特別純米酒 株式会社DHC酒造
越乃梅里 特別純米酒 秋あがり 株式会社DHC酒造
朝日晴 上撰 株式会社DHC酒造
北雪 吟醸酒 株式会社北雪酒造
菊水の辛口 菊水酒造株式会社
越後杜氏 本醸造 辛口 金鵄盃酒造株式会社
特撰 純米酒 越後桜 越後桜酒造株式会社
本醸造 白龍 白龍酒造株式会社お値打ち熱燗部門
★金賞
越の寒中梅 美味辛口 新潟銘醸株式会社
長者盛 千萬長者 新潟銘醸株式会社
特別本醸造 大洋盛 大洋酒造株式会社
古蔵のしずく 純米吟醸 越つかの酒造株式会社プレミアム燗酒部門
★金賞
純米大吟醸50 PAIR 吉乃川株式会社
越後雪紅梅 大吟醸 長谷川酒造株式会社
越の寒中梅 特別本醸造 新潟銘醸株式会社
田友 純米吟醸 高の井酒造株式会社
たかの井 特別純米 高の井酒造株式会社
田友 特別純米 高の井酒造株式会社
越乃八豊純米吟醸 株式会社越後酒造場
越乃雪椿 純米大吟醸 特A山田錦 雪椿酒造株式会社
純米大吟醸 越後桜 越後桜酒造株式会社
越後桜38 大吟醸 越後桜酒造株式会社特殊ぬる燗部門
★金賞
2011年 長期熟成古酒 悠久乃杜 吉乃川株式会社
オールド代々泉 越つかの酒造株式会社 - 2022.06.13 雪椿酒造(株)柏露酒造(株)市島酒造(株)高野酒造(株)吉乃川(株)菊水酒造(株)尾畑酒造(株)(株) DHC酒造青木酒造(株)朝日酒造(株)津南醸造(株)
- 2022年度Kura Master受賞酒発表
下記の通り2022年度Kura Master受賞酒が発表されました。
新潟県の受賞蔵は以下の通りでした。純米酒部門 プラチナ賞
真野鶴 毎毎純米 尾畑酒造株式会社
純米酒部門 金賞
郷 VINO 津南醸造株式会社
君の井 山廃 純米吟醸 君の井酒造 株式会社
人と木と ひととき 木桶仕込み純米酒 今代司酒造株式会社
越乃雪椿 純米吟醸 「花」 雪椿酒造株式会社
雪男 純米酒 青木酒造株式会社純米大吟醸酒部門 プラチナ賞
みなも中汲み純米大吟醸原酒 広島吟醸酵母 吉乃川株式会社
純米大吟醸酒部門 金賞
夢 純米大吟醸 王紋酒造株式会社
越路吹雪 純米大吟醸 越淡麗35 高野酒造株式会社
越乃雪椿 純米大吟醸 月の玉響 雪椿酒造株式会社
越乃雪椿 越淡麗 雪椿酵母仕込 純米大吟醸 雪椿酒造株式会社
越乃梅里 五百万石 純米大吟醸 株式会社DHC酒造
柏露 純米大吟醸 無濾過生貯蔵原酒 柏露酒造 株式会社
ほまれ麒麟 純米大吟醸 下越酒造株式会社
越乃雪椿 Grand-Cuvée 純米大吟醸原酒 雪椿酒造株式会社
蔵光 菊水酒造株式会社サケ スパークリング部門 金賞
久保田 スパークリング 朝日酒造株式会社
古酒部門 金賞
AGED 真野鶴 純米酒 佐渡金山貯蔵古酒 尾畑酒造株式会社
- 2022.05.31 雪椿酒造(株)石本酒造(株)池浦酒造(株)宮尾酒造(株)樋木酒造(株)妙高酒造(株)市島酒造(株)吉乃川(株)原酒造(株)菊水酒造(株)(株) DHC酒造お福酒造(株)越後桜酒造(株)玉川酒造(株)(株)松乃井酒造場白龍酒造(株)八海醸造(株)河忠酒造(株)栃倉酒造(株)大洋酒造(株)
- 新潟県の令和3酒造年度全国新酒鑑評会 入賞酒
独立行政法人酒類総合研究所
日 本 酒 造 組 合 中 央 会から
令和3酒造年度全国新酒鑑評会の入賞酒目録が発表されました。入賞酒とは、成績が優秀と認められた出品酒です。
金賞酒(☆印)とは、入賞酒のうち特に成績が優秀と認められた出品酒です。酒蔵名 銘柄
吉乃川株式会社 吉乃川
お福酒造株式会社 お福正宗 ☆
栃倉酒造株式会社 米百俵 ☆
河忠酒造株式会社 想天坊
妙高酒造株式会社 妙高山
原酒造株式会社 越の誉
玉川酒造株式会社 越後ゆきくら
高の井酒造株式会社 たかの井 ☆
池浦酒造株式会社 和楽互尊
八海醸造株式会社 八海山 ☆
苗場酒造株式会社 苗場山 ☆
石本酒造株式会社 越乃寒梅
樋木酒造株式会社 鶴の友 ☆
株式会社DHC酒造 越乃梅里 大吟醸 ☆
有限会社加藤酒造店 金鶴
峰乃白梅酒造株式会社 峰乃白梅 ☆
菊水酒造株式会社 節五郎蔵 菊水 ☆
王紋酒造株式会社 王紋
大洋酒造株式会社 大洋盛 ☆
宮尾酒造株式会社 〆張鶴
雪椿酒造株式会社 越乃雪椿
近藤酒造株式会社 菅名岳
越後桜酒造株式会社 越後桜
白龍酒造株式会社 白龍 ☆
麒麟山酒造株式会社 麒麟山
株式会社松乃井酒造場 松乃井 ☆
- 2022.05.14 雪椿酒造(株)石本酒造(株)新潟銘醸(株)高の井酒造(株)妙高酒造(株)(名)渡辺酒造店市島酒造(株)高野酒造(株)吉乃川(株)原酒造(株)菊水酒造(株)(資)竹田酒造店尾畑酒造(株)(株) DHC酒造金升酒造(株)頚城酒造(株)天領盃酒造(株)越後桜酒造(株)越銘醸(株)(株)北雪酒造(有)加藤酒造店(株)越後鶴亀八海醸造(株)弥彦酒造(株)君の井酒造(株)栃倉酒造(株)津南醸造(株)大洋酒造(株)
- インターナショナル ワイン チャレンジ2022 「SAKE部門」メダル受賞酒発表
「インターナショナルワインチャレンジ2022」のSAKE部門の審査がロンドンにて行われ、メダル受賞酒が決定しました。
新潟県内の酒蔵の受賞状況は下記のとおりです。SAKE SAMURAI Official Web Site 酒サムライ公式ウェブサイト<受賞酒一覧>
①純米酒の部
★GOLD 八恵久比岐 DAICHI 頚城酒造株式会社
SILVER 越後鶴亀 すずみさけ純米生貯蔵 株式会社越後鶴亀
SILVER 真野鶴 毎毎純米 尾畑酒造株式会社
BRONZE 越後鶴亀 なごみさけ無濾過純米 株式会社越後鶴亀
BRONZE 越の誉 淡麗純米 彩 原酒造株式会社
BRONZE 雅楽代~玉響~ 天領盃酒造株式会社
BRONZE 田人馬 白 津南醸造株式会社
BRONZE 根知男山 山廃純米 合名会社渡辺酒造店
COMMENDED 王紋 純米旨口 エンブレム 王紋酒造株式会社
COMMENDED 越乃梅里 特別純米酒 蔵出し原酒 株式会社DHC酒造
COMMENDED 越後鶴亀 純米 株式会社越後鶴亀
COMMENDED 越路乃紅梅 純米 五百万石 頚城酒造株式会社
COMMENDED 特別純米妙高山 妙高酒造株式会社
COMMENDED 山廃特別純米 サケ×サケ 大洋盛 大洋酒造株式会社②純米吟醸酒の部
SILVER 越乃梅里 純米吟醸 株式会社DHC酒造
SILVER 越弌 Episode1.1 株式会社越後鶴亀
BRONZE 越路乃紅梅 純米吟醸 八反錦 頚城酒造株式会社
BRONZE 峰乃白梅 純米吟醸 峰乃白梅酒造株式会社
COMMENDED 悠天 純米吟醸 株式会社DHC酒造
COMMENDED 北雪 純米吟醸 越淡麗 株式会社北雪酒造
COMMENDED 越乃寒梅 純米吟醸 灑 石本酒造株式会社
COMMENDED 越の寒中梅 金ラベル 純米吟醸 新潟銘醸株式会社
COMMENDED 雅楽代 天領盃酒造株式会社③純米大吟醸の部
SILVER 浩和蔵 純米大吟醸No.340 八海醸造株式会社
SILVER 八海山 純米大吟醸 八海醸造株式会社
SILVER 純米大吟醸 初花 金升酒造株式会社
SILVER 蔵光 菊水酒造株式会社
SILVER 越乃雪椿Grand-Cuvee純米大吟醸原酒 雪椿酒造株式会社
BRONZE 浩和蔵 純米大吟醸No.165 八海醸造株式会社
BRONZE 浩和蔵 純米大吟醸No.613 八海醸造株式会社
BRONZE 山城屋 ファーストクラス 越銘醸株式会社
BRONZE 越路乃紅梅 純米大吟醸 越淡麗 頚城酒造株式会社
BRONZE 伊乎乃 特別純米 高の井酒造株式会社
BRONZE みなも中汲み純米大吟醸原酒 K-1801 吉乃川株式会社
BRONZE みなも中汲み純米大吟醸原酒 新潟 S-9酵母 吉乃川株式会社
BRONZE 月の玉響 雪椿酒造株式会社
COMMENDED 純米大吟醸 越後桜 越後桜酒造株式会社
COMMENDED 浩和蔵 純米大吟醸No.504 八海醸造株式会社
COMMENDED 八海山純米大吟醸雪室貯蔵9年 八海醸造株式会社
COMMENDED 蝦夷富士 純米大吟醸 八海醸造株式会社
COMMENDED 北雪 純米大吟醸 越淡麗 株式会社北雪酒造
COMMENDED 錦鯉 丹頂 今代司酒造株式会社
COMMENDED 越乃寒梅 純米大吟醸 無垢 石本酒造株式会社
COMMENDED 越乃寒梅 純米大吟醸 金無垢 石本酒造株式会社
COMMENDED 純米大吟醸妙高山 妙高酒造株式会社
COMMENDED 真野鶴 純米大吟醸原酒 尾畑酒造株式会社
COMMENDED 真野鶴 純米大吟醸 佐渡山田錦 尾畑酒造株式会社
COMMENDED 真野鶴 実来 純米大吟醸 尾畑酒造株式会社
COMMENDED 越路吹雪 純米大吟醸 越淡麗 35 高野酒造株式会社
COMMENDED たかの井 純米大吟醸 高の井酒造株式会社
COMMENDED 郷 DINER 津南醸造株式会社
COMMENDED 彌彦 純米大吟醸 弥彦酒造株式会社
COMMENDED みなも中汲みjyunnmai純米大吟醸原酒 広島吟醸酵母 吉乃川株式会社
COMMENDED 越乃雪椿 純米大吟醸 Craft Master 雪椿酒造株式会社④本醸造の部
SILVER 君の井 上泉 本醸造 君の井酒造株式会社
COMMENDED 本醸造 金鶴 有限会社加藤酒造店
COMMENDED ふなぐち菊水一番しぼり 菊水酒造株式会社
COMMENDED 本醸造妙高山 妙高酒造株式会社
COMMENDED たかの井 特別本醸造 高の井酒造株式会社⑤吟醸の部
BRONZE 八海山 吟醸 八海醸造株式会社
BRONZE 越乃寒梅 吟醸酒 特撰 石本酒造株式会社
COMMENDED 越の寒中梅 吟醸生貯蔵 新潟銘醸株式会社
COMMENDED 吟醸極上吉乃川 吉乃川株式会社⑥大吟醸の部
★GOLD みなも山田錦中汲み大吟醸原酒 吉乃川株式会社
★GOLD みなも中汲み大吟醸原酒 広島吟醸酵母 吉乃川株式会社
SILVER 越の誉 大吟醸 原酒 越神楽 原酒造株式会社
SILVER 越の鶴 大吟醸 鑑評会出品酒 越銘醸株式会社
BRONZE 越乃梅里 大吟醸原酒 越淡麗磨き35% 株式会社DHC酒造
BRONZE かたふね 大吟醸斗瓶仕様 合資会社 竹田酒造店
BRONZE 彌彦 大吟醸 弥彦酒造株式会社
COMMENDED 王紋 吟の慶 大吟醸 王紋酒造株式会社
COMMENDED 越後桜38 大吟醸 越後桜酒造株式会社
COMMENDED 越後桜 première 大吟醸 越後桜酒造株式会社
COMMENDED 北雪 大吟醸YK35 株式会社北雪酒造
COMMENDED 越乃寒梅 大吟醸 超特撰 石本酒造株式会社
COMMENDED 真野鶴 万穂 磨三割五分大吟醸 尾畑酒造株式会社⑦古酒の部
SILVER 2011年 長期熟成古酒 悠久乃杜 吉乃川株式会社
BRONZE AGED 真野鶴 純米酒 金山貯蔵古酒 尾畑酒造株式会社
COMMENDED 壱九九六 純米吟醸 栃倉酒造株式会社⑧普通酒の部
SILVER こしのはくせつ 普通酒 極 弥彦酒造株式会社
BRONZE 越乃寒梅 生もと系酒母 柱焼酎仕込 特醸酒 石本酒造株式会社
BRONZE 君の井 越乃酔鬼 君の井酒造株式会社
COMMENDED 朝日晴 佳撰 株式会社DHC酒造
COMMENDED 越乃寒梅 普通酒 白ラベル 石本酒造株式会社
COMMENDED 越後の銘酒 妙高山 妙高酒造株式会社
COMMENDED 米百俵 伝統の酒 栃倉酒造株式会社
COMMENDED 厳選辛口吉乃川 吉乃川株式会社⑨スパークリングの部
COMMENDED 瓶内二次発酵酒 あわ 八海山 Hakkaisan Brewery Co., Ltd.
COMMENDED 酒蔵の淡雪プレミアム 吉乃川株式会社
- 2022.03.24 雪椿酒造(株)新潟銘醸(株)市島酒造(株)吉乃川(株)原酒造(株)長谷川酒造(株)尾畑酒造(株)(株) DHC酒造越後桜酒造(株)玉川酒造(株)峰乃白梅酒造(株)(株)越後鶴亀金鵄盃酒造(株)
- ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2022発表
ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2022が発表されました。
新潟県内の受賞蔵は以下の通りでした。最高金賞
メイン部門
大吟醸 越後桜 越後桜酒造株式会社
越乃梅里 純米吟醸 株式会社DHC酒造スパークリングSAKE部門
越の誉 発泡純米酒 あわっしゅ 原酒造株式会社
プレミアム大吟醸部門
月の玉響 雪椿酒造株式会社
プレミアム純米部門
越弌 純米吟醸 株式会社越後鶴亀
金賞
メイン部門
真野鶴 毎毎純米 尾畑酒造株式会社
越乃雪椿 純米吟醸 花 雪椿酒造株式会社
越の寒中梅 濃醇旨口 新潟銘醸株式会社
越の寒中梅 金ラベル 新潟銘醸株式会社
越後鶴亀 すずみさけ 純米生貯蔵 株式会社越後鶴亀
越後鶴亀 純米 株式会社越後鶴亀スパークリングSAKE部門
酒蔵の淡雪 プレミアム 吉乃川株式会社
越後鶴亀 ワイン酵母仕込み スパークリング 株式会社越後鶴亀プレミアム大吟醸部門
越後雪紅梅 大吟醸 長谷川酒造株式会社
純米大吟醸 丹頂錦 新潟銘醸株式会社
越後杜氏 純米大吟醸 越淡麗 金鵄盃酒造株式会社
目黒五郎助 玉川酒造株式会社
越後ゆきくら 玉川酒造株式会社
蔵光 菊水酒造株式会社
越後鶴亀 特醸 純米大吟醸 株式会社越後鶴亀
越乃梅里 大吟醸原酒 越淡麗磨き35% 株式会社DHC酒造
王紋 大吟醸 王紋酒造株式会社プレミアム純米部門
越乃雪椿 純米吟醸 雪椿酵母仕込 雪椿酒造株式会社
峰乃白梅 純米吟醸 峰乃白梅酒造株式会社
田友 特別純米 手造りプレミアム 高の井酒造株式会社
田友 特別純米 高の井酒造株式会社
越の誉 特別純米 彩 原酒造株式会社
越乃梅里 越淡麗 純米吟醸 株式会社DHC酒造 - 2021.12.22 雪椿酒造(株)加賀の井酒造(株)市島酒造(株)菊水酒造(株)尾畑酒造(株)越後桜酒造(株)宝山酒造(株)八海醸造(株)
- BORDEAUX SAKE CHALLENGE2021受賞酒発表
ワインの王国ボルドーで開催されたBORDEAUX SAKE CHALLENGEの受賞が発表されました。
新潟県の受賞は下記の通りです。プラチナ賞
純米吟醸の部
雪椿酒造
金賞
純米大吟醸の部
菊水酒造
八海山醸造
尾畑酒造
市島酒造
加賀の井酒造大吟醸の部
越後桜酒造
純米吟醸の部
宝山酒造
雪椿酒造
加賀の井酒造普通酒
宝山酒造銀賞
純米大吟醸の部
八海山醸造
加賀の井酒造普通の部
越後桜酒造
スパークリング
八海山醸造
銅賞
大吟醸の部
八海山醸造
尾畑酒造 - 2021.08.17 雪椿酒造(株)白瀧酒造(株)新潟銘醸(株)吉乃川(株)菊水酒造(株)尾畑酒造(株)(株) DHC酒造(株)越後酒造場越後桜酒造(株)(株)北雪酒造金鵄盃酒造(株)津南醸造(株)大洋酒造(株)
- 全国燗酒コンテスト 2021 審査結果
全国燗酒コンテスト実行委員会が主催した全国燗酒コンテスト2021の結果が発表になりました。
新潟県の受賞蔵をご紹介します。お値打ちぬる燗部門
720ml 1,100円以下(税別)又は 1.8L 2,200円以下(税別)審査温度:45℃
最高金賞

越乃白雁 黒松 中川酒造株式会社

菊水の辛口 菊水酒造株式会社

越淡麗 純米吟醸 雪椿酒造株式会社金賞
越の寒中梅 濃醇旨口 新潟銘醸株式会社
吉乃川 純米酒 PAIR 吉乃川株式会社
佳撰甘雨 株式会社越後酒造場
越乃梅里 特別純米酒 株式会社DHC酒造
越乃雪椿 純米吟醸 花 雪椿酒造株式会社
越後杜氏 本醸造 辛口 金鵄盃酒造株式会社お値打ち熱燗部門
720ml 1,100円以下(税別)又は 1.8L 2,200円以下(税別)審査温度:55℃
最高金賞

越乃梅里 吟醸 株式会社DHC酒造金賞
吟醸 十八代玉風味 玉川酒造株式会社
越の寒中梅 美味辛口 新潟銘醸株式会社
淡麗辛口 魚沼純米 白瀧酒造株式会社
越後の辛口純米酒 株式会社越後酒造場
北雪 金星 株式会社北雪酒造
菊水の純米酒 菊水酒造株式会社
白鳥蔵 越後桜酒造株式会社プレミアム燗酒部門
720ml 1,100円超(税別)かつ 1.8L 2,200円超(税別)審査温度:45℃
最高金賞

純米大吟醸50 PAIR 吉乃川株式会社金賞
田友 特別純米 高の井酒造株式会社
真野鶴 毎毎純米 尾畑酒造株式会社
純米吟醸 大洋盛 大洋酒造株式会社
村松 金鵄盃酒造株式会社特殊ぬる燗部門
にごり酒・古酒・樽酒・極甘酒など 審査温度:45℃
金賞
郷(GO) VINTAGE 津南醸造株式会社
越後の甘口純米酒 株式会社越後酒造場 - 2021.05.26 今代司酒造(株)雪椿酒造(株)白瀧酒造(株)石本酒造(株)池浦酒造(株)柏露酒造(株)新潟銘醸(株)宮尾酒造(株)樋木酒造(株)高の井酒造(株)原酒造(株)菊水酒造(株)長谷川酒造(株)尾畑酒造(株)(株) DHC酒造逸見酒造(株)越後桜酒造(株)越銘醸(株)玉川酒造(株)(株)北雪酒造白龍酒造(株)麒麟山酒造(株)八海醸造(株)青木酒造(株)弥彦酒造(株)高千代酒造(株)君の井酒造(株)千代の光酒造(株)津南醸造(株)大洋酒造(株)
- 全国新酒鑑評会の結果について
令和2酒造年度全国新酒鑑評会(新潟県)
(順不同)★金賞受賞
蔵元名 銘柄
中川酒造 越乃白雁
原酒造 越の誉
高の井酒造 初梅
新潟銘醸 長者盛
白瀧酒造 上善如水
青木酒造 鶴齢
石本酒造 越乃寒梅
樋木酒造 鶴の友
大洋酒造 大洋盛
宮尾酒造 〆張鶴
白龍酒造 白龍
麒麟山酒蔵 麒麟山★入賞
越銘醸 越の鶴
諸橋酒造 越の景虎
長谷川酒造 雪紅梅
柏露酒造 柏露
君の井酒造 君の井
千代の光酒造 千代の光
玉川酒造 玉梅
池浦酒造 和楽互尊
高千代酒造 たかちよ
八海醸造 八海山
津南醸造 霧の塔
今代司酒造 今代司
DHC酒造 越の梅里
逸見酒造 真稜
尾畑酒造 真野鶴
北雪酒造 北雪
菊水酒造 菊水
雪椿酒造 雪椿
越後桜酒造 越後桜
弥彦酒造 こしのはくせつ - 2021.05.19 今代司酒造(株)雪椿酒造(株)白瀧酒造(株)柏露酒造(株)新潟銘醸(株)田中酒造(株)高の井酒造(株)妙高酒造(株)(名)渡辺酒造店市島酒造(株)吉乃川(株)原酒造(株)菊水酒造(株)(資)竹田酒造店尾畑酒造(株)(株) DHC酒造頚城酒造(株)(株)北雪酒造越つかの酒造(株)(有)加藤酒造店八海醸造(株)君の井酒造(株)大洋酒造(株)
- インターナショナル ワイン チャレンジ2021発表
インターナショナル ワイン チャレンジ2021
「SAKE部門」メダル受賞酒の発表がされました。新潟県内の酒蔵の受賞は以下の通りでした。
<受賞酒一覧>
①純米酒の部
SILVER 越後鶴亀 しぼりたて 純米原酒 株式会社越後鶴亀
SILVER 根知男山 山廃純米 合名会社渡辺酒造店
BRONZE 越後鶴亀 純米 株式会社越後鶴亀
BRONZE 君の井 山廃 純米 君の井酒造株式会社
BRONZE 伊乎乃 特別純米 高の井酒造株式会社
BRONZE 人と 木と ひととき 純米原酒 びんかん 木桶仕込み 今代司酒造株式会社
BRONZE 王紋 純米旨口 エンブレム 市島酒造株式会社②純米吟醸酒の部
SILVER 越乃梅里 純米吟醸 株式会社DHC酒造 新潟県
SILVER 越後鶴亀 純米吟醸 株式会社越後鶴亀
SILVER 柏露 無濾過原酒 生貯蔵酒 純米吟醸 柏露酒造株式会社
BRONZE 北雪 純米吟醸 越淡麗 株式会社北雪酒造③純米大吟醸の部
★GOLD 越路乃紅梅 純米大吟醸 頚城酒造株式会社
★GOLD たかの井 純米大吟醸 高の井酒造株式会社
★GOLD 白瀧 セブン 純米大吟醸 白瀧酒造株式会社
SILVER 純米大吟醸 越後桜 越後桜酒造株式会社
SILVER みなも中汲み純米大吟醸原酒 K-1801酵母 吉乃川株式会社
SILVER かたふね 純米大吟醸 合資会社 竹田酒造店
SILVER 田人馬 白 津南醸造株式会社
SILVER 宣機の一本 純米大吟醸 白瀧酒造株式会社
BRONZE 蔵光 菊水酒造株式会社
BRONZE 王紋 純米大吟醸 伝臚 市島酒造株式会社
BRONZE 越乃雪椿 純米大吟醸 特A山田錦 雪椿酒造株式会社
BRONZE 浩和蔵 純米大吟醸 584 八海醸造株式会社
BRONZE 真野鶴 実来 純米大吟醸 尾畑酒造株式会社④本醸造の部
SILVER ふなぐち菊水一番しぼり 菊水酒造株式会社
SILVER 本醸造 金鶴 有限会社加藤酒造店⑤吟醸の部
BRONZE 五頭の雪 吟醸 越つかの酒造株式会社
BRONZE 越の寒中梅 吟醸生貯蔵 新潟銘醸株式会社
BRONZE 蓬莱 吟醸 伝統辛口 有限会社 渡辺酒造店⑥大吟醸の部
★GOLD みなも中汲み大吟醸原酒 広島酵母 吉乃川株式会社
SILVER 越の誉 大吟醸 原酒 越神楽 原酒造株式会社
SILVER 大吟醸 能鷹 田中酒造株式会社
SILVER 真野鶴 大吟醸無濾過原酒 瓶燗火入 尾畑酒造株式会社
BRONZE 大吟醸 妙高山 三割五分 妙高酒造株式会社⑧普通酒の部
SILVER 金乃穂 大洋盛 大洋酒造株式会社⑨スパークリングの部
BRONZE 瓶内二次発酵酒 あわ 八海山 八海醸造株式会社
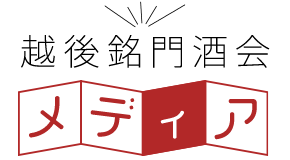
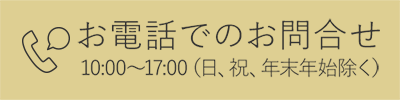
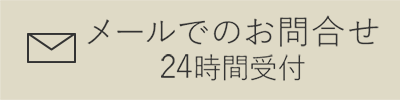

 雪椿 純米吟醸 花
雪椿 純米吟醸 花 清酒 ゆきつばき限定 純米吟醸
清酒 ゆきつばき限定 純米吟醸 清酒ゆきつばき 雪椿 純米大吟醸原酒生酒
清酒ゆきつばき 雪椿 純米大吟醸原酒生酒 清酒ゆきつばき 雪椿 純米大吟醸 特A山田錦
清酒ゆきつばき 雪椿 純米大吟醸 特A山田錦 清酒 雪椿 ゆきつばき 越後加茂 純米 新潟限定
清酒 雪椿 ゆきつばき 越後加茂 純米 新潟限定 清酒 雪椿 ゆきつばき 純米吟醸 越淡麗
清酒 雪椿 ゆきつばき 純米吟醸 越淡麗 清酒 雪椿 ゆきつばき 純米
清酒 雪椿 ゆきつばき 純米 清酒 雪椿ゆきつばき 雪椿酵母仕込み 純米吟醸
清酒 雪椿ゆきつばき 雪椿酵母仕込み 純米吟醸 清酒 雪椿 ゆきつばき 月の玉響 純米大吟醸
清酒 雪椿 ゆきつばき 月の玉響 純米大吟醸